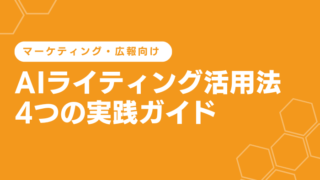マーケティングに生成AIを使えていますか?
生成AIは目覚ましい進化を遂げており、昨日できなかったことが今日できるようになることも珍しくありません。
生成AIの自然言語レベルがアップデートされるなどの従来機能の改善はもちろん、推論に優れたモデル、インターネットの情報を網羅的に調べてまとめる「Deep Research」機能、引用源や思考プロセスの明示など、初期モデルからすると、かゆいところに手が届き始めている印象です。
そんな中、マーケティング担当者が生成AIに期待を寄せている施策の1つが、「SEO対策」。中でも、コンテンツマーケティングと呼ばれる、コンテンツ(主に記事)の検索順位を上げることでアクセス上昇を目指す施策ではないでしょうか。
本記事では、コンテンツマーケティングの専門家が実際に一筆書きした記事と、生成AIの中でも最も精度に優れる有料モデルの制作した記事を比較し、生成AIによるSEO対策が可能かについてお伝えします。
SEO記事制作にお困りの方へ

読者の“次の行動”まで設計する、AIより解像度の高いSEOコンテンツ作りのポイントや、成功事例などもお伝えします。まずは30秒で無料相談を。
【結論】生成AIでSEO対策(記事制作)を完全自動化することはできない

生成AIの登場からさまざまな方法でコンテンツ制作の自動化に取り組んできましたが、生成AIだけでSEO対策、つまり検索キーワードに対して上位に来るような記事を仕上げることは、現実的に難しいです。
専門家の目から見ると、事例の具体性やターゲットに寄り添った言葉の選び方が甘いです。方向性は合っていても、表現はほぼほぼ書き直すこともあります。
実際に「御託を並べるよりも見たほうが早い」と考えるあなたは、以下の2記事を比較してみてください。
※2つ目の記事はパスワードロックがかかっています。パスワードは「Rplus」です。
一方で、生成AIがSEO対策にまったく使えないかというと、そういうわけではありません。
どのサイトを見ても「生成AIの作ったたたき台を人が編集して、最適なアウトプットに仕上げましょう」という、月並みな結論が記載してあります。
しかし、この言葉だけではいまいちイメージがわかない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
では次に、SEO対策となりうる記事のライティングにおいて、AIがどのように活用できるのか、記載します。
SEO対策において生成AIが最も活用できるのは「リサーチ」「構成」「1次チェック」

最初に断っておくと、これからお伝えすることは、これまで成果を出してきた手法に基づく「ポジショントーク」です。
「読者が見た瞬間に意思決定できる解像度を持った、良質なコンテンツを届けたい」という想いに基づいています。
「そこそこの粒度でもいいから、まずはとにかくたくさんのコンテンツを作ったほうがよい」など、異なる考え方をする方もいらっしゃるので、あくまで軸の1つとして考えてください。
まず、SEO対策として記事のライティングを行う場合、丁寧にやっている企業だと、ステップは以下の9つにわかれます。
①:記事のゴールと誰に届けたいかの明確化
②:対策キーワードの選定
③:①②に基づく情報のリサーチ
④:構成の作成
⑤:文章の作成
⑥:文章やSEOの一般ルールに基づく1次チェック
⑦:専門家視点での2次チェック(E-E-A-Tの観点)
⑧:記事のWEBサイトへの入稿
⑨:記事の視認性や関連コンテンツ導線などユーザビリティチェック
上記のうち、SEO対策においてAIが活躍できると考えるのは、以下の3つです。それぞれのステップにおける有用性について解説します。
③:①②に基づく情報のリサーチ
④:構成の作成
⑥:文章やSEOの一般ルールに基づく1次チェック
※「⑨:記事の視認性や関連コンテンツ導線などユーザビリティチェック」にも有用ですが、今回はライティング文脈の話なので、割愛します。
情報リサーチ:単純作業工数の削減にてAIが寄与
情報の網羅性は、SEO記事ライティングにとって重要な点の1つです。
生成AIの登場以前は「狙っているキーワードでGoogle検索して、上位10記事に含まれるコンテンツに網羅性で負けないように」という話がよくありました。
そのため、人の手で1時間以上かけて上位10記事をリサーチし、情報を列挙し、先行コンテンツの模倣にならないように知っている情報も含めて並び替えや分類の仕方を考える…という作業が行われていました。
しかし、生成AIのDeep Research機能を使えば、10記事どころか100記事を調べ、ものの数分~数十分で網羅性のある情報のまとめができてしまいます。
よって、対策キーワードについて知見が深くなくても、ある程度の方向性がつかむことが可能になります。
また、対策キーワードについて知見はあるが、SEOやライティングに詳しくない方でも、伝えるべき情報のヌケモレを防ぐことができるのです。
今までは「ハルシネーション」と呼ばれる、いわゆる「嘘つき情報」も中に混じっていることが問題視されていましたが、Deep Researchが引用源を示してくれるようになったため、嘘つきリスクも比較的下がってきています。
単純作業の工数を削減する意味では、情報リサーチにおけるAIの貢献度は計り知れないでしょう。
構成の作成:異なる切り口の生成においてAIが寄与
SEO対策においては、「いかにうまくライティングするか」というテクニカルな部分を重視する企業もありますが、特に弊社が最も大事だと考えるのが、「構成の作成」です。
極論すると、構成(≒切り口)さえ面白ければ、何を書いても評価されると考えています。
しかし、切り口を変えてシナリオを構成し直すというのは、プロであっても至難の業です。
どうしてもコンテンツに対する先入観・情報不足などが邪魔をし、一面的なものの見方に偏ってしまう。仕方がないことです。
そこで、生成AIの出番です。たとえば、同じテーマであっても「誰の目線で語るか」によって構成は変わりますし、「誰に対する目線で語るか」によっても構成は変わります。
変数が増えれば増えるほど、人の頭では再思考するのに時間がかかりますが、生成AIであればすぐにアイデアを出してくれます。
もちろん、アイデア自体が良いものに仕上がるかどうかは「神のみぞ知る」ですし、提案された構成が一語一句使えたことは、過去ありません。
しかし、短時間で新たなものの見方を与えてくれる意味で、生成AIは大いに活用できるといえます。
「構成をお任せできる」という意味合いではないので、ご注意ください。
チェック:当たり前レベルのミスを精度高く抽出する点でAIが寄与
何千記事と監修してきたディレクターとして著しくテンションが下がることがあります。それは、誤字脱字や表記揺れなど、「しょうもないミス」を発見し、指摘することです。
直してしまえば早いのですが、同じミスを繰り返されると負荷になるため、いちいち指摘が発生します。
そして、更にテンションが下がるのが、そういった「しょうもないミス」を見逃してしまい、提出先の最終責任者に指摘されることです。
これくらいの話であれば「校正チェックツール」などを使えばカバーできるかもしれません。
ただ、記事を書き続けていると、当たり前レベルであってもどんどんリクエストが増えていきます。
たとえミス率が1%の人であっても、ルールが100個あったら毎回1つはミスしてしまう計算になります。
「神は細部に宿る」ということで、凡ミスに妥協はしたくありませんが、人間なのでミスもしてしまう。こういった悩みを解決できるのが、生成AIです。
生成AIに文章そのものを校正させると面白くない表現になって返ってくることもあるので、ルールに則っていない可能性がある部分を指して、提案してもらうように使うのがおすすめです。
人がどうしても見逃してしまうところまで細かく目を光らせてくれる意味で、生成AIが活用できるといえます。
SEO記事ライティングそのものに生成AIは使わないほうがよい?
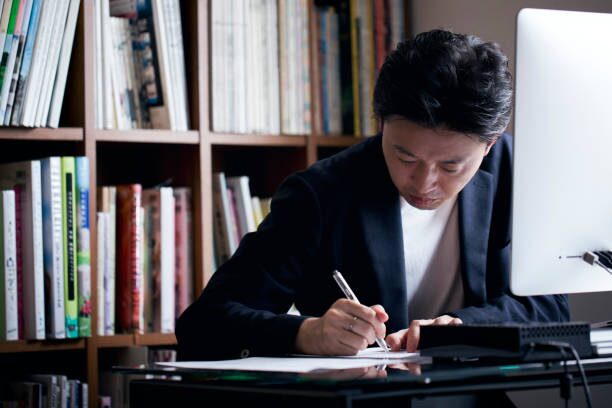
SEO記事ライティングの中で、最も生成AIを役立てたいのは「ライティング」でしょう。しかし、ライティングそのものに生成AIを使うことは、あまりおすすめしません。
とはいえ、「何千文字と書かなければいけない記事のたたき台を作ってくれるんだから、ちょこっと編集すれば工数削減になるのでは?」という意見もわかります。
結論、使わないほうがよい理由としては「編集難易度が高いから」です。
「編集難易度が高い」だけお伝えしてもイメージがわきにくいため、具体的な理由の中で特に大きな要因だと考えられるものを3つ挙げます。
今回は「AIで生成したライティングの編集難易度が高い」というお話に絞るため、そもそも生成AIではカバーしきれない「一次体験や具体的な事例を出力できない」という、当たり前の課題については割愛します。
①:言葉の絶妙なニュアンスに違和感が出る
たとえば、AIは「業務が増えててんやわんやしている」という言葉は使いません。「業務が増えて対応に追われている」と出力するでしょう。
しかし、相手の大変さがわかっていることを伝えるために、あえて「てんやわんや」という表現を用いることもあるでしょう。
この絶妙なニュアンスにこだわることで、読み手に親近感を持ってもらったり、具体的なアクションを起こす壁を乗り越えてもらったりできることを、プロのマーケターは知っています。
だからこそ、生成AIをSEO記事ライティングそのものに使うことで、無難で緩急のない表現にまとまってしまうのはデメリットだと考えます。
②:不要な情報まで出力される
SEO記事ライティングでは、網羅性が重要だということはお伝えしました。一方で、網羅性を重視しすぎて、読者にとって不要な情報までたくさん出してしまうと、逆に視聴負荷が上がってしまいます。
たとえば、「生成AI 導入例」というキーワードを対策するとします。読者はおそらく生成AIについて知ったうえで、どのように応用できるかを探していることが想定されます。
この場合、「生成AIとは」「生成AIの仕組み」のような話は、すでに知った上で検索をしている可能性が高いです。
一方で、生成AIが書く文章は「要らない部分の引き算」まで配慮することはできません。どのような内容を引き算するか言語化することも、テーマや状況によって変わるため、難しいでしょう。
情報の要不要を仕分ける工数が発生してしまう点も、ライティングに生成AIを使うデメリットだと言えます。
③:情報にストーリー性を持たせにくい
決定的なのは、情報が見出しごとに完結してしまい、全体にストーリー性を持たせにくいことです。
読みやすく行動につながりやすいSEO記事ライティングには、「なぜこの言葉がこの順番で並んでいるのか」について、明確な意思と、意思に基づくストーリーがあります。
生成AIに「前の文章と因果関係を持たせて」と指示することはできますが、全体で見るとどうもちぐはぐに仕上がってしまう。
あげくの果てに、前半で言っていた内容と同じ意味の文章を後半でも繰り返すことも珍しくありません。
SEOにおいて、表面上はまねできても、各社の特徴が出るのがストーリーだと考えており、ストーリーを持たせようとすると、生成AIが出力するような一般的な型にハマらないことも少なくありません。
ライティングに生成AIを使うデメリットは、上記のような重要な側面でも出てきてしまうのです。
SEO記事ライティングに生成AIを使ってもよい企業の特徴2選

これまでの情報を踏まえて、生成AIをうまく使ってレベルの高いSEO記事ライティングができるイメージがわくでしょうか。
ハイレベルな編集スキルとAIリテラシーが求められるため、社内にSEOに精通した専任部隊を持たない限り、内製化はおすすめしません。
ただし、以下の2パターンに当てはまる場合は、使ってもよいと考えます。
①:記事制作担当者の工数削減または最低限の質を担保するために、指針として出力するパターン
②:とにかくコンテンツの数を担保しておいて、後から編集して質を上げるパターン
①については、SEO記事を外注する費用の捻出が難しいが、内部の人間が専門性を持ち合わせていない状況を想定しています。
この場合は、素人が短期間で努力したり、単価の安いライターに依頼するよりも質の高いアウトプットが期待できるため、苦肉の策として生成AIでSEOライティングまで行ってもよいでしょう。
ただし、近いうちに競合他社も同じことをやってくる可能性があるため、慣れてきたら構成までは自社で考えることをおすすめします。
②については、急スピード急成長を求められている状況を想定しています。
この場合は、四の五の言わずとにかく早く成果物を出すことに優先順位を置かれていることもあるかと思います。
それであれば、とにかく競合他社より早くコンテンツを出すことで、検索エンジンが評価するタイミングを前倒しできるため、やむを得ず生成AIでSEOライティングまで行ってもよいでしょう。
どちらのパターンにも言えるのですが、生成AIのコンテンツはいずれコモディティ化しますし、特にGoogleはオリジナリティのない生成AIコンテンツを規制する方法を考えてくる可能性が高いです。
必ずオリジナリティの高いコンテンツを追って入れるなど、編集することを前提にご活用ください。
(おまけ)SEO対策に特化したAIライティングツールのおすすめ”0選”

最後に、「SEO対策に特化したAIライティングツールもあるけど、普通の生成AIと比べてどうなの?」という疑問にお答えします。
結論、2025年3月時点では「なし」です。サービスを紹介したほうがSEO的には評価が上がるのですが、それでも忖度せずにお伝えします。
※特定のツールやサービスを批判するものではありません。あくまで編集部の所感としてお伝えします。
まず、「SEO対策に特化したAIライティングツール」とは、SEO記事を書く際にプロのマーケターが考えていることを分解して、わざわざ自分でプロンプトに書かなくても、フォーマットに記入さえすればその思考を再現したうえで生成AIに指示できる、といったものです。
これだけ聞くと、「良さそうじゃん」と思うかもしれません。
しかし、第三者ツールに引っ張ってこられる生成AIのAPIはまだ旧モデルにしか対応しておらず、高度な推論や自然言語に対応した有料モデルのほうが精度が高いのが現状です。
つまり、SEOに特化したAIライティングツールを導入するのであれば、有料版ChatGPTの最高性能モデルを導入したほうが、精度が高い印象です。
では、「生成AIを使いこなすリソースもないから、安く外注しよう」と考えて、AIライティングサービスを導入するのはどうでしょうか。
残念ながら、安ければ安いほどやめたほうがよいです。
そもそも「生成AIは使いこなせるが、文章の良し悪しを判断できない」ケースや、「生成AIは使いこなせるが、発注者のサービスに寄り添って書かれていない」ケースが後を絶ちません。
運良く上位表示されてもコンテンツの薄さから逆ブランディングになってしまう可能性まであります。
どんなにコストを落としたとしても、外注前提でまっとうなSEO記事に仕上げることを考えれば、半分以上の工程を内製化しない限りは1記事10,000円を切ることはありません。
1記事10,000円以内のコストパフォーマンスを謳っているサービスを検討する場合は、どこかの工程が手抜きされているか、半分程度の工程を内製化できていることを前提に意思決定してください。
生成AIをうまく活用してSEO対策やライティング内容を強化しよう

生成AIのクオリティが急成長しているからこそ、マーケティングを頼りたく気持ちもわかります。
しかし、生成AIで通り一遍のコンテンツは誰でも書き出せるからこそ、生成AIに収まらない、情熱や個性、型破りな発想が価値をもたらし、価値に気がついた読者が行動を起こす。そんな流れが訪れる日もまた遠くはないでしょう。
弊社、Rplus株式会社では、生成AI時代も手を抜かず、とことん質を突き詰めるスタイルのSEO記事ライティング・コンテンツマーケティングを行っています。
採用率5%未満の、高い品質基準に継続的に応えられるライター、ディレクターのみでチームを構成しており、C向け、B向けともに幅広い実績があります。
読者に胸を張って価値をもたらせるコンテンツをお持ちの企業様は、ブランド価値を高めながら広げていくお手伝いができますので、ぜひ無料相談からご連絡ください。
SEO記事制作にお困りの方へ

読者の“次の行動”まで設計する、AIより解像度の高いSEOコンテンツ作りのポイントや、成功事例などもお伝えします。まずは30秒で無料相談を。